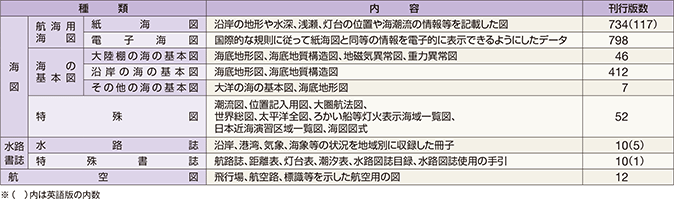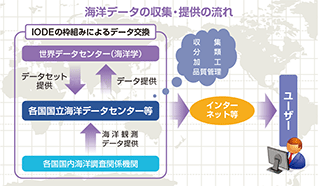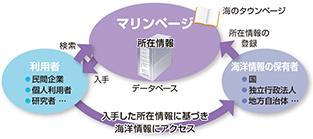海洋は、海運や水産業、資源開発、マリンレジャー等、様々な目的で利用されており、それぞれの目的によって必要となる情報が異なります。海上保安庁では、海洋調査により得られた多くの海洋情報を基に、それぞれの目的に合わせ、ユーザーが利用しやすい形での情報提供に努めています。

海上保安庁では、船舶の安全航行に不可欠な海図や電子海図情報表示装置(ECDIS)で利用できる航海用電子海図(ENC)等の作製・刊行を行っています。
令和6年には、海洋調査により得られた最新情報を基に、海図(改版17図)、水路書誌(新刊1冊、改版5冊)等を刊行しました。
海洋情報は、船舶の航行の安全や、資源開発、マリンレジャー等の様々な目的で利用されています。
このため、ユーザーが目的に応じて、利用しやすいように海洋情報を提供することが非常に重要となっています。
海上保安庁は、日本海洋データセンター(JODC)として、長年にわたり海上保安庁が独自に収集した情報だけでなく、国内外の海洋調査機関によって得られた海洋情報を一元的に収集・管理し、インターネット等を通じて国内外の利用者に提供しています。
また、海洋基本計画に基づき、各機関に分散する海洋情報の一元化を促進するため、国の関係機関等が保有する様々な海洋情報の所在について、一元的に検索できる「海洋情報クリアリングハウス(マリンページ)」を平成22年3月より運用しています。
さらに、平成28年7月の総合海洋政策本部決定及び平成30年5月に閣議決定された第3期海洋基本計画に基づき、海上保安庁では、我が国の海洋状況把握(MDA)の能力強化に向けた取組の一環として、海洋情報を集約・共有するための情報サービス「海洋状況表示システム」(海しる)を運用しています。
「海しる」は、海上安全、自然災害対策、海洋環境保全、海洋産業振興等様々な分野での利活用を目的として、内閣府の総合調整のもと、海洋情報を集約し、オンラインの地図上で重ね合わせ表示ができるサービスです。「海しる」では、政府及び政府関係機関が収集・提供している海洋情報を一元的に利用いただくことができます。日本の周辺海域のみならず、衛星情報を含む広域の情報や気象・海象のようなリアルタイムの情報も掲載しており幅広くご利用いただけます。
令和4年からは、海洋教育コンテンツの提供を開始しました。さらに外部のアプリやシステム上で「海しる」のデータを直接扱えることのできるよう「海しるAPI*」の提供についても開始しました。これまでは「見る」だけの「海しる」でしたが、これからは「使う海しる」へと利便性向上のための取組を進めています。
令和5年には、12月に我が国の海洋状況把握(MDA)構想、令和6年4月に海洋開発等重点戦略が総合海洋政策本部により策定され、「海しる」への更なる情報の一元化のため、API連携等により官民の保有する海洋情報の集約が求められるなど「海しる」の重要性が益々高まっています。
令和6年の取組としては、関係省庁・機関等にご協力いただき、「海しる」に地理的表示(GI)登録産品(水産物、水産加工品等)、台風経路図、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域等の多様な分野の情報を新規に掲載しました。さらに、区画漁業権、定置漁業権、共同漁業権や海岸清掃活動等各種情報の更新を行い、合計250以上の情報の提供を維持しています。また、「海しるAPI」については96項目を公開しており、各種サービスに活用されています。
*API:Application Programing Interfaceの略。ソフトウェアやアプリケーションの一部を外部に向けて公開することで他のソフトウェアと機能を共有できるようにするもの。
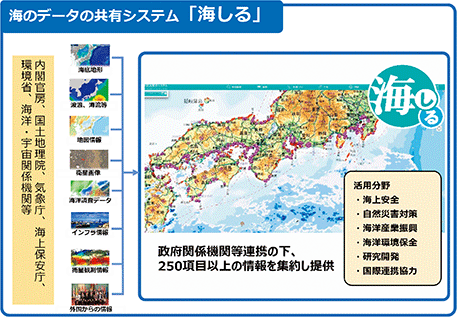
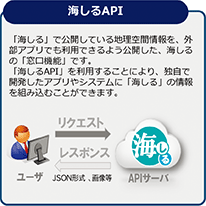
近年、世界中でDX化が著しく進んでおり、海洋分野に関しても例外ではありません。このような海洋のDX化にかかる取り組みは、海上保安庁に留まるものではなく、関係行政機関・産業界等にも大きく関わります。
例えば、内航船業界では、船員の高齢化・船員不足の問題が深刻と言われています。この問題に対応すべく、(一財)日本船舶技術研究協会を中心に50を超える産官学の団体が、日本財団の助成により船舶海洋分野の無人化・省人化に資するダイナミックマップ(自動運航に資する静的・動的な情報サービス)の研究開発を進めており、海上保安庁の航海情報には高い需要があります。このため、令和6年度は、同協会の「船舶ダイナミックマップに用いる次世代航海情報の利活用に関する連絡会」に海上保安庁職員も参加し、関係機関やステークホルダーと実務者間で議論を交わしました。
引き続き、海洋調査等によって得られた最新情報を基にして、海図等の水路図誌等を刊行していきます。
国際水路機関(IHO)では、次世代航海情報表示装置(次世代ECDIS)における利用のため、新たな航海情報の規格であるS-100シリーズの開発を進めています。このS-100シリーズの一つであるS-101に基づいた電子海図では、リアルタイム情報を含む他のS-100シリーズに基づいた航海情報を重ね合わせて表示できるため、利便性と安全性がさらに向上します。海上保安庁においてもS-100シリーズに基づいた航海情報の提供に向けて準備を進めていきます。
また、JODCをはじめ、海洋情報クリアリングハウス(マリンページ)、海しるの管理・運用を適切に行うとともに、政府機関や関係団体等との連携を一層強め、掲載情報の充実や機能の拡充に努めます。これらの取組を通じて、目的に合わせて利用しやすい海洋情報の提供を推進していきます。