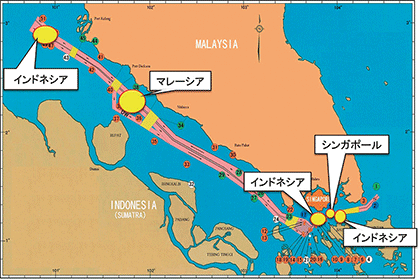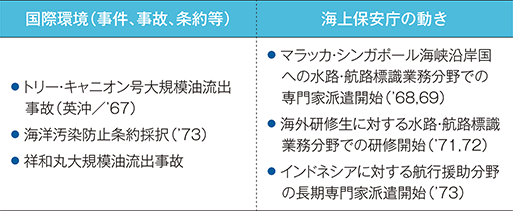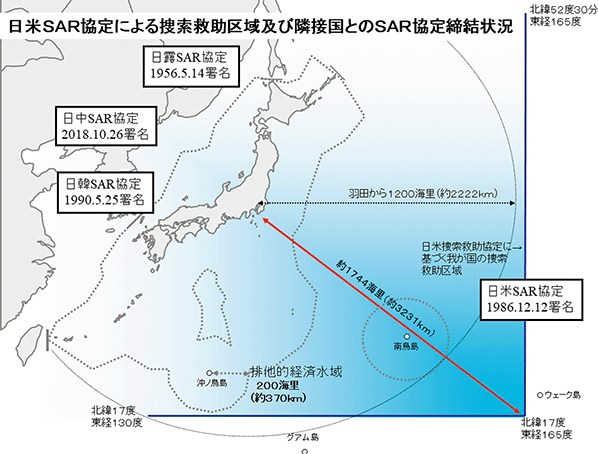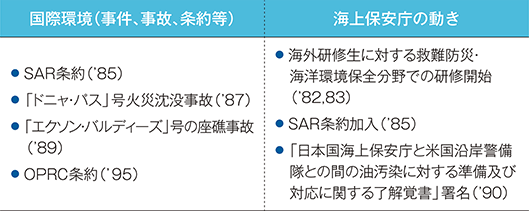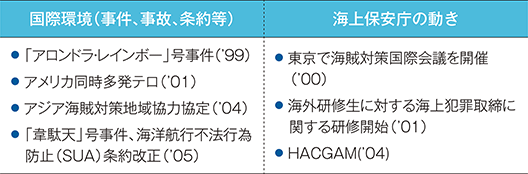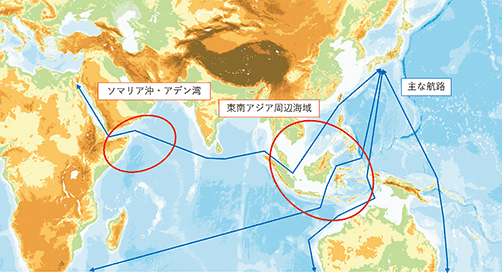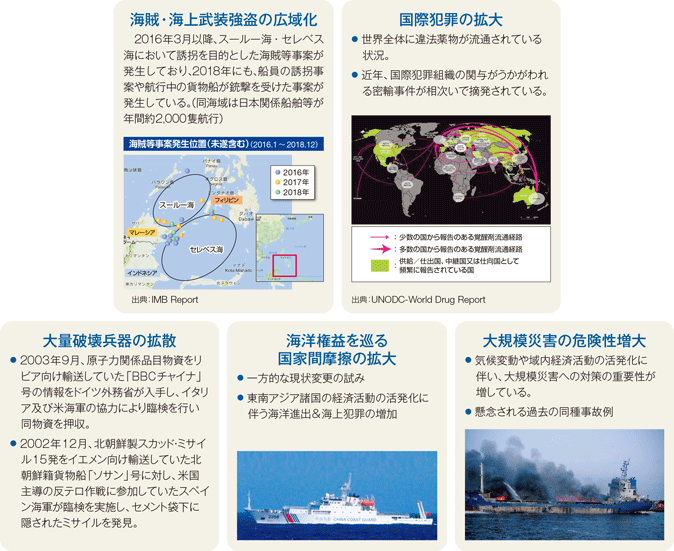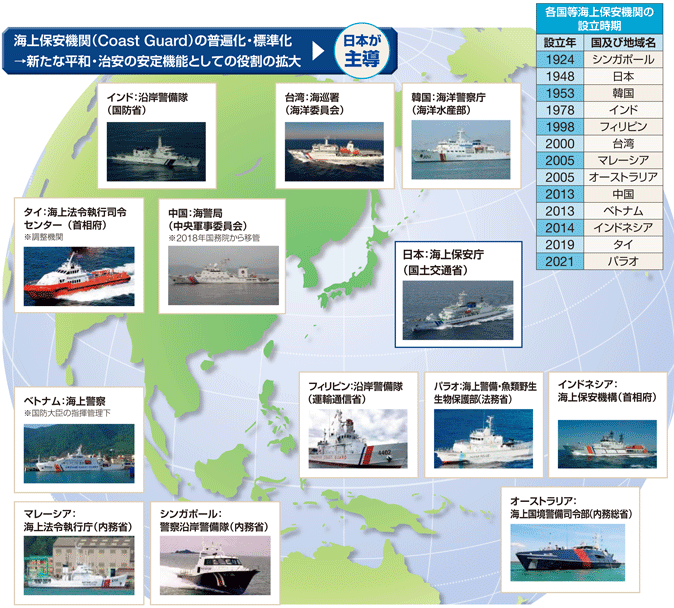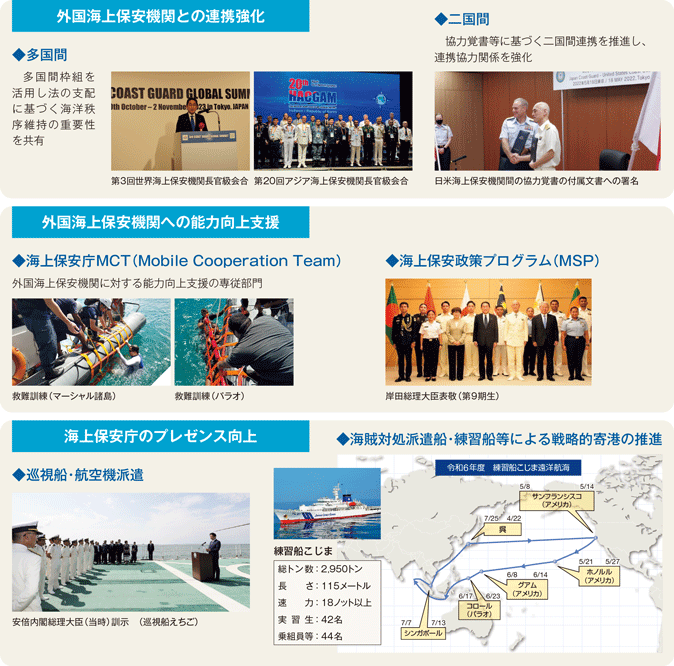1960�N��`
- �}���b�J�E�V���K�|�[���C���̐��H���ʓ����獑�ۋ��͂��J�n
- ��1968�N�}���b�J�E�V���K�|�[���C�����ݍ��Ƃ̋������ʂ��J�n
- ��1971�N���ۋ��͋@�\�iJICA�j�ۑ�ʌ��C�u���H���ʃR�[�X�v�J�n
1980�N��`
- �C��{���E�~���iSAR�j����h������ō��ۘA�g���i�W
- ��1985�N�u1979�N�̊C��ɂ�����{���y�ы~���Ɋւ��鍑�ۏ��iSAR���j�v����
2000�N��`�@�C�m�ɂ�����u�@�̎x�z�v�̍��܂�
- �C���̑�����e�����Ă��_�@�ɁA�����ԘA�g���X�Ɋg��
- ��2000�N�u�k�����m�C��ۈ��t�H�[�����iNPCGF�j�v���J�Ái�����j
- ��2004�N�u�A�W�A�C��ۈ��@�֒�������iHACGAM�j�v���J�Ái�����j
2010�N��`
- �u���R�ŊJ���ꂽ�C���h�����m�v�̎����Ɍ����O���[�o���A�g�Ɋg��A�@���s����̔\�͌���x��������
- ��2015�N�u�C��ۈ�����v���O�����iMSP�j�v�J�u
- ��2017�N�u���E�C��ۈ��@�֒�������iCGGS�j�v���J�Ái�����j
- ��2017�N�u�C��ۈ������o�C���R�[�|���[�V�����`�[���iMCT�j�v����
- ��2019�N�u���ې헪���v����
����A�W�A���ӊC��A���ɁA�}���b�J�E�V���K�|�[���C���́A�����n��Ɖ䂪�������ԃV�[���[���̗v�Ղł���A�C���ʗʂ����債�����x�o�ϐ������ȍ~�A���̊C��ɂ����鎡���̈ێ��ƊC���ʂ̈��S�m�ۂ́A�䂪���ɂƂ��ďd�v�Ȃ��̂ł����B�������Ȃ���A1950�N�㓖���̓���A�W�A�����́A�C��ɂ����鎡���̈ێ���C���ʂ̈��S�m�ۓ��̋Ɩ����s�Ɋւ��A�g�D�A�̐��A�Z�p�̖ʂɂ����ĕs�\���ł��邱�Ƃ�����A�䂪������̎x�����������߂��Ă��܂����B
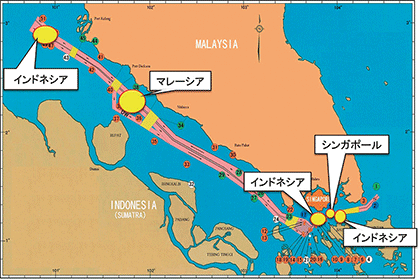
�}���b�J�E�V���K�|�[���C���i�������ʍđ��ʑΏۊC��j
©���v���c�@�l �}���b�J�C�����c��
���̂��߁A�C��ۈ����ł́A����A�W�A�����ɑ��āA�C��ۈ��@�ւ̐ݗ��x����A�C��ۈ������L���鍂�x�ȋZ�p�E�m���̈ړ]���s�����Ƃœ���A�W�A���ӊC��ɂ�����C��ۈ��\�͂̑S�̓I�Ȍ����}��A�����̊C��̎����̈ێ��ƊC���ʂ̈��S�m�ۂɍv�����܂����B
�Ȃ��ł��A�C��ۈ����̍��ۋ��̗͂��j�̓}���b�J�E�V���K�|�[���C���ɂ����鐅�H���ʂ���n�܂�܂����B�����A���C���̊C�}�͐�O�̐��H���ʂɂ��쐬���ꂽ���̂ŁA�ʍq�D�����ɐڐG���鎖�̂��������Ă��܂����B���C���͉䂪���V�[���[���̗v�Ղł��邽�ߍ������狭���v�]������A���ݍ�����̍����M���Ɗ��҂��āA1968�N����C��ۈ����̓C���h�l�V�A�E�}���[�V�A�E�V���K�|�[���Ƌ����Ő��H���ʂ����{���A1982�N�ɐV���ȊC�}�����s����܂����B�C�}�ɂ͍��x�ȑ��ʋZ�p�ɂ���Ĕ������ꂽ�����̐��L�ڂ���A�ʍq�D�������S�ȍq�H��I���ł���悤�ɂȂ�܂����B
�����A���ō��ꂽ�C�}�͉䂪���̎x���ɂ���ēd�q�C�}�ɒu�������A���C���̓d�q�C�}�͐��E�ōł����p�����d�q�C�}�̈�ƂȂ��Ă��܂��B���݁A�O���[�o���o�ς̔��W�ɂ�蓯�C���̊C���ʗʂ͊i�i�ɑ����܂������A���̑b�͊C��ۈ������x���������H���ʂɂ���ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��ł��傤�B

�D�����t�s����l�q�i1970�N��V���K�|�[���`�t�߁j
�����I�ȏ�ɂ킽�鍑�ۍv��
�`�C�}�쐻�Z�p����̎x���`
���ۍq�C�̈��S���m�ۂ��邽�߂ɂ́A�䂪���݂̂Ȃ炸�A�J���r�㍑���܂߁A���E���̍q�H��`�ŊC�}����������Ă���K�v������܂��B�C�}�ɂ́A���ې��H�@�ցiIHO�j�ɂ����č��ۓI�Ȋ���݂����Ă��܂����A�e���̊C�}�쐻�҂̋Z�p�͂��\���łȂ��ꍇ�A���̊�������C�}�����s���邱�Ƃ��ł��܂���B
�����ŁA�C��ۈ����ł́A1971�N���甼���I�ȏ�ɂ킽��A���ۋ��͋@�\�iJICA�j�Ƌ��͂��āA�J���r�㍑�̐��H���ʂ�C�}�쐻�Ɍg���Z�p�҂ɑ��āA�C�}�쐻�ɕK�v�ƂȂ邳�܂��܂ȗ��_��Z�\�̏K���A�n�k�E�Ôg�̖h�Ћy�ъC�m���ی�Ɋւ���m���̕t�^����ړI�Ƃ���JICA�ۑ�ʌ��C�u�C�}�쐻�Z�p�R�[�X�v�����{���Ă��܂��B

JICA�ۑ�ʌ��C�J�n�����̗l�q

���ۉ�c�Ŕ�������}���[�V�A���H�����iJICA���C�C�����j
1988�N�ɂ́A���i�R�ŊJ�Â��ꂽ��11��FIG/IHO���ې��H���ʋZ�p�Ҏ��i����ψ���iIBSC�j�ł̌����ȐR�����o�āA����B�����̌��C�@�ւƂ��ĊC��ۈ������H���i���C�m��j���F�肳��A�{�R�[�X�͗��N���猤�C�C���҂ɑ��āA����JICA�����{���邳�܂��܂Ȍ��C�̒��ō��۔F�莑�i���t�^�����B��̃R�[�X�ƂȂ�܂����B���̌�A�{�R�[�X�ɂ�2004�N�ɔ��������X�}�g�����n�k�E�C���h�m�Ôg�ɂ���Q���ӂ܂��A2006�N�x����͓����̃J���L�������ɒÔg�h�ЂɊւ�����e���������ق��A2011�N�x����́A�n�����V�X�e���iGIS�j��C�m���ۑS�Ɋւ���Ȗڂ��[��������ȂǁA����ɉ����ċ��߂��Ă�����e��������Ȃ��獡���Ɏ���܂��B���݂́u�C�}�쐻�Z�p�R�[�X�v�́A�l�ވ琬�ɌW��IHO�̍��ۉ�c�ł͔��ɍ����]������Ă���A�܂��A2024�N�x�ɂ̓V���K�|�[�����H�����������S�ŏ��߂ăI�u�U�[�o�[�Ƃ��ĎQ������ȂǁA�J���r�㍑�ȊO����̒��ڂ��傫���Ȃ��Ă��܂��B
�{�R�[�X�̌��C�ł́A���N10�����x�̌��C�����A��5�����ԁA�Q�H���Ƃ��ɂ��Ȃ���ۑ�Ɏ��g��ł��܂��B���C�͍��w�����ł͂Ȃ��A�C��ۈ����̑��ʑD�ł̊C�m���K��h�Њ֘A�{�ݓ��̌��w�ɉ����A�ŏI�I�ɂ͎��H�I�ȍ`�p�̑��ʎ��K��4�T�Ԃ����Ď��{���A�C�}�̊�b�f�[�^�ƂȂ鑪�ʌ��}��1�l1���쐻���܂��B���ʌ��}���쐻���邽�߂ɂ͐������̍H�����o��K�v������܂����A���C�����炪�A��O��Ƃ��D���K�œ������ʃf�[�^����́E�v�Z��������i�K����s�����ƂŁA�Z�p�̏K�����m���Ȃ��̂Ƃ��邾���łȂ��A�f�[�^�𐳂������߂��A�]������\�͂�{�����Ƃ��ړI�Ƃ��Ă��܂��B
�l�ވ琬��ʂ����J���r�㍑�̋Z�p�͌���́A�S���E�̊C�̈��S�ƌo�ϊ��������x�����Ă��邱�Ƃɂق��Ȃ�܂���B����܂łɎ����ɖ߂������C���̑����́A�e�����H���ǂ̊����Ƃ��Ċ��A�e���̐��H�Ɩ����������Ă��܂����B���H���ʊW�̍��ۉ�c�ɏo�Ȃ���ƁA�{���C�̏C���������̑�\�Ƃ��ďo�Ȃ��Ă��邱�Ƃ�����������܂���B���������A���C���C���������C������̎�ŁA���݊C���`�p�̒��������{����A�C�}�̍ŐV�ێ����s���邱�Ƃ����҂��Ă��܂��B
���e���̋���@�ւ����{���鐅�H���ʋZ�p�җ{���R�[�X�ɑ��A���H���ʓ��̍��ۊ���߂鍑�ۈψ���iIBSC�j�ɂ��F�肳��鎑�i�ŁA����A���AB����2�ɕ������B

���ʌ��}���쐻����JICA���C��
�䂪�������x�o�ϐ������}����1960�N��A�����ȊC��A�����v�Ɏx�����A���D�Ƃ͉䂪���L���̎Y�ƂƂ��ď����ɔ��W�𐋂��܂����B���̊ԁA����^�D�̓o��������đD���̗A�o�ʂ�����I�ɑ��債�A�܂��A�C��A�����������剻���܂������A��^�D��댯���ύڑD�̑����ɔ�Ⴗ��`�ŁA��^�D���ɂ�鎖�̂��K�͂Ȗ����o���̓����������Ŕ�������悤�ɂȂ�܂����B
���������w�i����A���ۓI�ȑ{���~���̐����\�z����d�v���������悤�ɂȂ�A1985�N�Ɂu1979�N�̊C��ɂ�����{���y�ы~���Ɋւ��鍑�ۏ��iSAR���j�v���������܂����B�䂪���́A�����ւ̉����ɉ����A���V�A�A�A�����J�A�؍��A�����Ƃ̊ԂŌʂ̋���iSAR����j��������A�L�͂ȑ{���~������S�����邱�ƂƂȂ�܂����B
�܂��A��K�͂Ȗ����o���̂́A����1�����ɂƂǂ܂炸���ӂ̉��ݏ����ɍL�͂Ȕ�Q�������炷���Ƃ���A���̑�ɂ͊C�ɖʂ������X�ɂ�鋦�͑̐��̍\�z���������܂���B������������肪���E�I�ɃN���[�Y�A�b�v�����Ȃ��A1996�N�Ɂu1990�N�̖��ɂ�鉘���ɌW�鏀���A�Ή��y�ы��͂Ɋւ��鍑�ۏ��iOPRC���j�v���������A�C��ۈ����ł́A�ߗ����Ƃ̘A�g��ʂ��āA�����o���̂ւ̑Ή��\�͂̌����}��܂����B
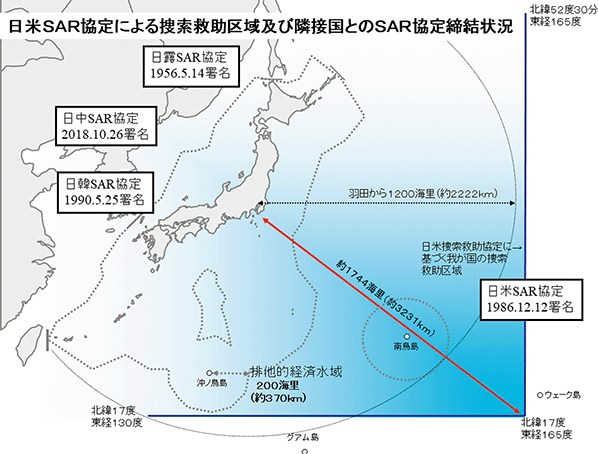
SAR���y��SAR���������

�Ċ؊C��ۈ��@�֑D���ɂ��\�h�K��

�v�~���҈��n���P��

�{���~���P��

�����p�ŏՓˁE���シ��LPG�^���J�[
2000�N��O��̃}���b�J�E�V���K�|�[���C���ł́A1999�N�ɔ��������A�����h���E���C���{�[�������ȂǁA���{�W�D�����܂ޑD���ɑ���d��ȊC���E�C�㕐�������������������Ă��܂����B���������܂��A�C��������������ɂ́A�A�W�A�e���̊C��ƍߎ���\�͂̌���y�јA�g�E���͊W�̋�����}��K�v�����邱�Ƃ���A2000�N4���ɓ����ɂ����ăA�W�A�n���15�̍��ƒn��̊W�@�ւ��ꓯ�ɉ���u�C���ۉ�c�v���J�Â���܂����B���̉�c�ɂ����āA�u�A�W�A�C����`�������W2000�v���̑�����A�Ȍケ��Ɋ�Â��ăA�W�A�n��ɂ�����C����̂��߂̑����Ԃɂ��A�g�E���͑̐����m������܂����B
���̂悤�Ȓ��A�e���̋��ʂ̌��O�ł���e�����Ђ̍��܂�ɑΉ����邽�߁A2004�N2���A�^�C�ŊJ�Â��ꂽ�u��4��C�������Ɖ�v�ɂ����āA�]���̊C����݂̂Ȃ炸�A�C��e�������e�Ƃ���C��Z�L�����e�B�̈ێ��̌��ʓI�ȕ�������������̊J�Â���Ă���܂����B
������A�C��ۈ�����2004�N6���A�����ɂ����āu�A�W�A�C��ۈ��@�֒�������iHACGAM)�v���J�Â��A����܂ō\�z���ꂽ�C��������ł̋��͑̐��W�����A�V���ɊC��e��������ł̋��͂��������邽�߂̎�g����������A�֘A���̌�����ړI�Ƃ��A����̎�g�y�јA�g�E���͂̎w�j�ƂȂ�u�A�W�A�C��Z�L�����e�B�E�C�j�V�A�`�u2004�v���̑�����܂����BHACGAM�́A���݂����E�e�n��Ōp�����A�J�Â���Ă��܂��B
�C��ۈ����ł́A���̂悤�ȑ����Ԃɂ��A�g�𐄐i���邱�Ƃɂ��A�A�W�A�n��ɂ�����C��Z�L�����e�B�̊m�ۂɓw�߂Ă��܂��B

HACGAM���������Q���E���w�����C���Ώ��A�g�P��

�u�A�����h���E���C���{�[�v����ǐՂ���C���h���x����

��1��HACGAM�̗l�q

�C��ۈ����̌Ăт����ɂ��J�Â��ꂽ�C���ۉ�c
�C����Ƃ��Ă̍��ۓI��g
�`COUNTER PIRACY 50-50�`
�䂪���́A�o�ϊ�����Љ���̊�ՂƂȂ�e��G�l���M�[�A�z���A���Y���A�_�앨�₻�̑������̑������C�O����A�����Ă���A�f�ʂ�99.6�p�[�Z���g�i�g�����x�[�X�j���C��A���Ɉˑ����Ă��܂��B���̂��߁A���ۖf�Ղ��x����V�[���[���̈��S���m�ۂ��邱�Ƃ́A�䂪���o�ς̔��W�⍑�������̈ێ��ɂƂ��ċɂ߂ďd�v�ł��B�������Ȃ���A�����Ȃ��C���y�ёD���ɑ���C�㕐�������i�ȉ��u�C�����v�j�ɂ��D�����g���ւ̔�Q�����₽���A�����̓��{�W�D�����ʍq����C���ʂ̗v�Ղł���u�}���b�J�E�V���K�|�[���C���v��u�\�}���A���E�A�f���p�v�̊C��ɂ����Ă��C�������Ă���������ȂǁA�D���ƊC���ʂ̈��S����������Ă��܂��B���̂��߁A�C��ۈ����ł́A����A�W�A���ӊC�擙�֏����D��q��@��h�����A�C����̂��߂̌��C��ł̂��傤���≈�ݍ��C��ۈ��@�ւƂ̍����A�g�P���A�@���s�\�͌���x�������s���ƂƂ��ɁA�C���Ώ��̂��߃\�}���A���E�A�f���p�ɔh�������C�㎩�q���̌�q�͂Ɏi�@�x�@�����ɔ����邽�߁u�\�}���A���ӊC��h���{�����v�Ƃ��ĊC��ۈ����悳����ȂǁA�C����Ƃ��Ă̗l�X�ȍ��ۓI��g�����{���Ă��܂��B
���̂��сA2000�N������{���Ă���u����A�W�A���ӊC��ւ̏����D�h���v���A2025�N1���̏����D�u�����v�ɂ��C�O�h����50����ƂȂ�A�܂��A2009�N����J�n�����u�\�}���A���ӊC��h���{�����v�̔h���ɂ��Ă��A2025�N2����50����i��50�����h���j���}���܂����B�i�ڍׂ��u�C��ۈ����̊C����v���Q�Ɓj
�\�}���A���ӊC��̊C����

�u�A�����h���E���C���{�[�iALONDRA RAINBOW�j�v������
1999�N10��22���A���{�̊C�^��Ђ��^�q����p�i�}�Љݕ��D�u�A�����h���E���C���{�[�v���i���g������8��g���j���}���b�J�E�V���K�|�[���C�����q�s���A����e�A�i�C�t�ŕ��������C���Ƀn�C�W���b�N����A���{�l2�����܂ޏ�g��17�����ċւ���܂������A���̌�A��g���͋~���{�[�g�ʼn������A11��9���S�������ɕی삳��܂����B����A�u�A�����h���E���C���{�[�v���̓C���h�m����q�s���̂Ƃ�����C���h���x�����y�уC���h�C�R�Ɏ�艟�������܂����B
�C��ۈ����͂��̎����Ɋւ��A�����D�y�эq��@��h�����A�{�����������{����ƂƂ��ɍq�s�x��o���t�ߍq�s�D���ɏ������{���܂����B

�u�A�����h���E���C���{�[�v��
�u��ʓV�v������
2005�N3��14���A�}���b�J�C�����q�s���̓��{�ЊO�m�^�O�u��ʓV�v���i���g����498�g���j���e���ŕ��������C���Ƀn�C�W���b�N����A���{�l2�����܂ޏ�g��3�����A�ꋎ���܂����B3��20���A�A�ꋎ��ꂽ3���́A�^�C�암�̉����Ń^�C�C��x�@�ɂ���Ė����ی삳��܂����B
�C��ۈ����͂��̎����Ɋւ��A�}���[�V�A���̉��ݍ��ɑ���^�D���̑{���y�я��̈˗����s���ƂƂ��ɁA�����W�̂��ߐE��2�������n�ɔh�����܂����B

�u��ʓV�v��
�ߔN�A�V������J���r�㍑�̑䓪�ɂ�萢�E�e���̃p���[�o�����X�ɑ傫�ȕω��������A���ێЉ���l���������ŁA�e���̊i���̖����\�ʉ����܂����B����ɂ́A�e���A�C���A���۔ƍ߁A��ʔj��̊g�U���̗l�X�ȋ��Ђ��������z���čL�����Ă���A�C�m���v�����鍑�ƊԂ̖��C���������Ă��܂��B���������w�i�̂��ƁA���{������b�́A2014�N5���A��13��A�W�A���S�ۏ��c�i�V�����O�����E�_�C�A���[�O�j�ɂ����������ɂ����āA�C��ɂ�����u�@�̎x�z�v�̓O��̊ϓ_����A3�̌����i�@�@�Ɋ�Â��咣�A�A�u�́v��p���Ȃ��A�B���a�I�������j������ق��A2016�N8���A��6��A�t���J�J����c�iTICAD VI�j�ɂ������u���ɂ����āA�u���R�ŊJ���ꂽ�C���h�����m�iFOIP: Free and Open Indo-Pacific�j�v�̊T�O����܂����B
���݂ł́A�����m����C���h�m���o�āA�����E�A�t���J�Ɏ���C���h�����m�n��ɂ����āA�@�̎x�z�Ɋ�Â����R�ŊJ���ꂽ�C�m�������������邱�Ƃ̏d�v�����A���ێЉ�ōL�����L����Ă��Ă��܂��B

��13��A�W�A���S�ۏ��c�i�摜�o�T�F�O����HP�j

��6��A�t���J�J����c�i�摜�o�T�F���@HP�j
�܂��A�C���h�����m�n��̌��������S�ۏ���ɒ��ʂ��钆�A�C���A�e���A��ʔj��̊g�U�A���R�ЊQ�A��@���ƂƂ������l�X�ȋ��Ђ͈�w���݉����Ă���A�n�揔�����u���R�ŊJ���ꂽ�C���h�����m�v�̎����Ɍ����ċ��͂���K�v���͂܂��܂����܂��Ă��܂��B
2000�N��ɓ���A�C��̌o�ϊ��������������Ă���A�W�A�n��ł́A�C��ۈ��@�ւ��������Őݗ�����܂����B����́A�l�X�ȊC�㋺�Ђ�C�m���v�����鍑�ƊԖ��C���g�債�Ă������ŁA�O���E�R���ɉ����āA�C��ۈ��@�ւ̏d�v���̔F�����L�����Ă��Ă��邱�Ƃ��w�i�ɂ���ƍl�����܂��B1948�N�ɒa���������{�̊C��ۈ����́A�ł����j�̌Â��A�����J���x�����ƕ��ѐ��E�̊C��ۈ��@�ւ̐��I���݂Ƃ��āA���E�̊C��ۈ��@�ւ̘A�g�E���͂����[�h������������҂���Ă��܂��B
���{�ɂ����āA�u���R�ŊJ���ꂽ�C���h�����m�v�̂��߂̐V���ȃv�����Ƃ��āA���a�̌����Ɣɉh�̃��[���A�C���h�����m���̉ۑ�Ώ��A���w�ȘA�����A�u�C�v����u��v�֊g������S�ۏ�E���S���p�̎�g���f�����Ă��܂��B
�C��ۈ����ł́A���ێЉ�ɂ�����C�m�����̈��艻�Ɍ�������g�Ƃ��āA�e���C��ۈ��@�ւƂ̘A�g�����A�e���C��ۈ��@�ււ̔\�͌���A�C��ۈ����̃v���[���X����Ƃ���3�̒��̎�g��i�߂Ă��܂��B
�u���R�ŊJ���ꂽ�C���h�����m�v�̂��߂̐V���ȃv����
- 1�@���a�̌����Ɣɉh�̃��[��
- 2�@�C���h�����m���̉ۑ�Ώ�
- 3�@���w�ȘA����
- 4�@�u�C�v����u��v�֊g������S�ۏ�E���S���p�̎�g
�C��ۈ����͊C��ɂ�����@���s�@�ւł���A�@�̎x�z�́u�K�[�f�B�A���v�Ƃ��āA�x�@��ጴ���̉��A�@�ɑ���A�C��̈��S�⎡���̊m�ۂ�}���Ă��܂����B�܂��A�u���R�ŊJ���ꂽ�C���h�����m�v�̎����̂��߁A�C�m�ɂ�����@�̎x�z�ɂ��C�m�������ێ�����Ƃ�������{�I���l�ς����L����e���Ƃ̘A�g�����A�C���h�����m���ݍ��ւ̔\�͌���x���𐄐i���Ă��܂����B
�����ŁA�ߔN�l�X�ȊC�㋺�Ђ�C�m���v�����鍑�ƊԖ��C���g�債�Ă��܂��B�����������������S�ۏ�����ɂ����Ă��A�C�m�ɂ�����u�@�̎x�z�v��3�̌����Ƃ�������{�I���l�ς��C���h�����m���ݍ��Ƌ��L���Ă������߂ɂ́A�����Ȃ��ʂɂ����Ă��A��ÂɁA���A�B�R�Ƃ��đΉ��ɓ�����@�̎x�z�̃K�[�f�B�A���ł��葱���邱�Ƃ��d�v�ł���A�C��ۈ������炪�A�@�̎x�z�̑̌��҂Ƃ��āA���E�̊C��ۈ��@�ւ��������Ă����K�v������܂��B
�C�m�ɂ�����@�̎x�z�E3�̌���
- 1�@���Ƃ͖@�Ɋ�Â��Ď咣���Ȃ��ׂ�����
- 2�@�咣��ʂ����߂ɗ͂�Ј���p���Ȃ�����
- 3�@���������ɂ͕��a�I�Ȏ��Ԃ̎��E��O�ꂷ�ׂ�����
�C��ۈ����̐Ӗ�
�C��ɂ�����@���s�@�ւƂ��āA�����Ȃ��ʂɂ����Ă���ÂɁA���A�B�R�Ƃ��đΉ����A�u�@�̎x�z�̃K�[�f�B�A���v�ł��葱����
�C��ۈ������ƂȂ�A�W�A���S�ۏ��c�ւ̎Q��
2024�N6��1���A�C��ۈ����̓V���K�|�[���ɂ����ĊJ�Â��ꂽ��21��u�A�W�A���S�ۏ��c�i�V�����O�����E�_�C�A���[�O�j�v�ɏ��߂ĎQ�����܂����B
�V�����O�����E�_�C�A���[�O�Ƃ́A�p�����ې헪�������iIISS�FThe International Institute for Strategic Studies�j����Â����ŁA���N�V���K�|�[���ɂ����āA�A�W�A�����m�n��̍��h��b�Ȃǂ������Q�����A�n��̉ۑ����S�ۏ�Ȃǂ��b�������Ă�����̂ł��B
���{���{����́A2006�N��薈�N�h�q�ȓ��̊W�{�Ȓ��������o�Ȃ��Ă���A�ߋ��ɂ͈��{������b�A�ݓc������b����u�����s���Ă��܂��B
����̉�ł́A�u�C��@���s�ƐM�������v�Ƃ����Z�b�V���������߂Đ݂����܂����B����́A���S�ۏ�ɂ�����C��@���s�@�ւ̖����Ƃ��̏d�v�������ۓI�ɂ����ڂ��W�߂Ă��邽�߂ł���ƍl�����܂��B
�C��ۈ����́A��̏�ɂ����āA�@�̎x�z�ɂ��C�m�����̈ێ��̏d�v���A�C��ۈ��@�ւ̉ʂ��������A�x�@���̌������̖@���s�ɂ�������͂̍s�g�Ɋւ���l�����A�C��ۈ��@�֊Ԃ̐M�������������炷�e���Ƃ������C�m�ɂ�����@�̎x�z�Ƃ������ՓI���l�ς̋��L��}��܂����B
�܂��A�A�����J�A�t�B���s���A�C���h�l�V�A�A�x�g�i����4�����̊C��ۈ��@�ւ̒����Ɠԉ�k�����{�����ق��A���ƂȂ���Ĕ�O���Ԓ�������k�����{���A�e���C��ۈ��@�ւ̍X�Ȃ�W�̐[���ƘA�g���͂̌p�����m�F���܂����B

���Ĕ�O���Ԓ�������k

����Ԓ�������k

����Ԓ�������k

��Ŕ������鐣���Ǖv�����i�����j

�Q�������C��ۈ��@��