近い将来に発生が懸念されている南海トラフ巨大地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震や首都直下地震に加え、近年、激甚化、頻発化し、深刻な被害をもたらす集中豪雨や台風など、自然災害への対策は重要性を増しています。
海上保安庁では、こうした自然災害が発生した場合には、人命・財産を保護するため、海・陸の隔てなく、機動力を活かした災害応急活動を実施しています。また、自然災害に備えた灯台等の航路標識の強靱化や防災情報の整備・提供、医療関係者等の地域の方々や関係機関との連携強化にも努めています。

|
5 災害に備える > CHAPTER II. 自然災害対策
5 災害に備える
CHAPTER II. 自然災害対策
近い将来に発生が懸念されている南海トラフ巨大地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震や首都直下地震に加え、近年、激甚化、頻発化し、深刻な被害をもたらす集中豪雨や台風など、自然災害への対策は重要性を増しています。 海上保安庁では、こうした自然災害が発生した場合には、人命・財産を保護するため、海・陸の隔てなく、機動力を活かした災害応急活動を実施しています。また、自然災害に備えた灯台等の航路標識の強靱化や防災情報の整備・提供、医療関係者等の地域の方々や関係機関との連携強化にも努めています。 近年、集中豪雨や台風等による深刻な被害をもたらす自然災害が頻発しています。 海上保安庁では、自然災害が発生した場合には、組織力・機動力を活かして、巡視船艇や航空機、特殊救難隊、機動救難士、機動防除隊等を出動させ、被害状況の調査を行うとともに、被災者の救助や行方不明者の捜索等を実施しています。 また、地域の被害状況やニーズに応じて、SNS等での情報発信を行いつつ、電気、通信等のライフライン確保のため、協定に基づき電力会社等の人員及び資機材を搬送するとともに、地方公共団体からの要請に基づく給水や入浴支援に加え、支援物資の輸送等の被災者支援を実施しています。 1 自然災害への対応
令和6年度も地震や台風、大雨等の自然災害が発生し、各地に被害をもたらしました。海上保安庁では、長年の海難における救助活動等で培った経験・技能や巡視船艇・航空機等の機動力を活用し、これらの自然災害に対応しました。また、航行船舶や海域利用者に対する情報提供等を行ったほか、地方公共団体に職員を派遣して最新の被害状況等の情報収集を実施し、各地域のニーズに応じた支援を実施しました。 大雨への対応
令和6年7月、梅雨前線の影響で、東北地方を中心に記録的な大雨となり、各地で被害が発生しました。海上保安庁では、航空機による被害状況の調査を実施したほか、孤立集落が発生した山形県からの要請に基づき、回転翼機及び機動救難士によって、孤立者2名の吊上げ救助を実施しました。 
台風への対応
令和6年8月末、鹿児島県に上陸した台風第10号は、九州・四国地方を通り東海道沖へと進行し、九州地方を中心に、全国的に大雨や強風被害をもたらしました。海上保安庁では、台風の接近、上陸に際し、人命救助を最優先として、巡視船艇・航空機等を配備させ、即応体制を確保するとともに、被害状況の調査や行方不明者の捜索を実施しました。また、地方公共団体に職員を派遣し、被害状況等の情報収集を行うとともに、電力会社との協定に基づき、鹿児島県・山口県で巡視船艇により停電復旧作業のための電力会社職員及び資機材の離島搬送を実施しました。 地震への対応
令和6年8月8日、宮崎県日向灘を震源とするマグニチュード7.1の地震が発生し、最大震度6弱が観測されました。海上保安庁では、直ちに、巡視船艇・航空機等を発動させ、被害状況の調査を実施するとともに、航行警報及び海の安全情報を発出し、付近航行船舶等への情報提供を行いました。 同日には、南海トラフ地震臨時情報が発表され、政府からの特別な注意の呼びかけが行われたことに伴い、海上保安庁としては、南海トラフ地震防災対策推進地域を管轄する管区を中心に、巡視船艇・航空機等の即応体制を継続的に確保するとともに、海の安全情報による情報発信、巡視船艇からの周知・呼びかけを行ったほか、港則法に基づく勧告を実施するなど、海事関係者をはじめ、一般市民に対しても広く情報提供を実施しました。 2 東日本大震災からの復旧・復興に向けた取組
海上保安庁では、引き続き第二管区海上保安本部を中心に、東日本大震災からの復旧・復興に向けた取組を実施しています。 令和6年においても、地方公共団体の要望に応じ、潜水士による潜水捜索や警察、消防との合同捜索を実施しています。 1 海上交通の防災対策
海上保安庁では、近年、激甚化、頻発化する自然災害においても、海上交通の安全確保を図るため、国土強靱化基本計画に基づき、「走錨事故等防止対策」、「航路標識の耐災害性強化対策」及び「航路標識の老朽化等対策」に取り組み、灯台をはじめとする航路標識関係施設の強靱化を推進しています。 また、船舶交通がふくそうする東京湾、伊勢湾、大阪湾を含む瀬戸内海では、湾外避難などの勧告・命令制度や、同制度に基づく措置を円滑に行うための官民の協議会を設置するなどして、走錨に起因する事故の防止に取り組んでいます。 
2 防災情報の整備・提供
海上保安庁では、災害発生時の船舶の安全や避難計画の策定等の防災対策に活用していただくため、防災に関する情報の整備・提供も行っています。西之島をはじめとする南方諸島や南西諸島等の火山島や海底火山については海底地形調査、火山の活動状況の監視を実施し、付近を航行する船舶の安全に支障を及ぼすような状況がある場合には、航行警報等により航行船舶への注意喚起等を行っています。 そのほかにも、船舶の津波避難計画の策定等に役立つように、大規模地震による津波被害が想定される港湾及び沿岸海域を対象に、予測される津波の到達時間や波高、流向・流速等を記載した「津波防災情報図」を「海しる」のテーマ別マップ等で、インターネットにて公開しています。 また、「海の安全情報」において、自然災害に伴う港内における避難勧告、航行の制限等の緊急情報のほか、気象現況等を提供しています。 3 海底地殻変動観測の実施
日本周辺の海溝では日本列島がある陸側プレートの下に海側のプレートが沈み込んでいます。海側プレートの沈み込みに伴う陸側プレートの変形によって蓄積されたひずみが、プレート境界面上のすべりとして急激に解放されることで、海溝型地震が発生すると考えられています。海上保安庁では、GNSS*測位と水中音響測距技術を組み合わせた海底地殻変動観測を平成12年度から行っています。この観測では、将来の海溝型地震の発生が予想される南海トラフや、東北地方太平洋沖地震後の挙動が注目される日本海溝沿いの海底に観測機器を設置し、測量船を用いてプレートの変形に伴う海底の動き(地殻変動)を調べています。 観測によって得られる、地震発生前のひずみの蓄積過程や地震時のひずみの解放等に伴う海底地殻変動データは、陸上のGNSS観測では知り得ない貴重な情報を有しており、海溝型地震の発生メカニズムの解明において非常に重要な役割を果たしています。海上保安庁は、地震調査研究推進本部や気象庁の南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会に参加し観測結果を報告することで、地震・地殻活動の評価に貢献しています。 *GPS等の人工衛星から発射される信号を用いて地球上の位置等を測定する衛星測位システムの総称 4 関係機関との連携・訓練
自然災害に対して、迅速かつ的確に対応するためには、地方公共団体や関係機関との連携が重要です。 海上保安庁では全国各地の海上保安部署に配置した地域防災対策官を中心に、平素から地方公共団体や関係機関等と顔の見える関係を築き、情報共有や協力体制の整備を図るとともに、非常時における円滑な通信体制の確保や迅速な対応勢力の投入等、連携強化を図ることを目的に合同訓練を実施しています。 令和6年度は、285回、関係機関等との合同訓練を実施しました。 また、主要な港では、関係機関による「船舶津波対策協議会」を設置し、海上保安庁が収集・整理した津波防災に関するデータを活用しながら、港内の船舶津波対策を検討しています。 激甚化・頻発化する自然災害への対応をより一層強化していくため、海上保安庁では、巡視船艇・航空機等の必要な体制の整備をはじめ、各種訓練の実施、地方公共団体や関係機関との連携強化、防災情報の的確な提供、地震・地殻活動の評価への貢献、航路標識の強靱化、走錨に起因する事故の未然防止など、引き続き各種取組を推進していきます。 孀婦海山で海底噴火の痕跡を確認 〜令和5年10月 鳥島近海の地震・津波関連〜
令和5年10月9日早朝に鳥島近海を発生源とする津波が発生し、八丈島で波高0.7mを記録したほか、関東から奄美大島にかけて広範囲に津波が観測されました。しかし、小規模な地震は発生していましたが、津波を引き起こすような地震が観測されなかったことから発生原因が不明でした。 海上保安庁では10月20日に羽田航空基地所属の航空機で上空から鳥島近海を観測したところ、鳥島の西方約50kmの海上で南北80kmにわたって連なる軽石状の浮遊物を認めました。この発見により、それまで不明だった津波の発生源が海底の火山噴火である可能性が高まりました。 海底の火山噴火の有無を確かめるために、令和6年1月に測量船「拓洋」により鳥島近海の海底地形調査を実施しました。今回取得した海底地形データと令和4年12月に独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)が取得した海底地形データを比較した結果、過去に噴火を起した記録がない「孀婦海山」と呼ばれる海底火山において、新たに直径約1.6kmの火口が形成されていることが分かりました。 これらの情報や他機関の様々な情報を考慮すると、「孀婦海山」で発生した海底噴火が10月9日に発生した津波に関係したと考えられます。 海上保安庁では、引き続き海域火山の調査を実施し、得られた成果は火山調査研究推進本部をはじめ関係機関と共有して火山活動状況の把握などに役立てていきます。  軽石状の浮遊物(令和5年10月20日) 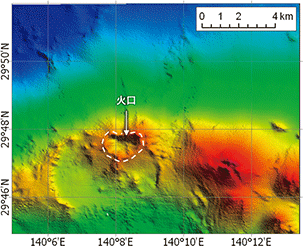 測量船「拓洋」による海底地形(令和6年1月) 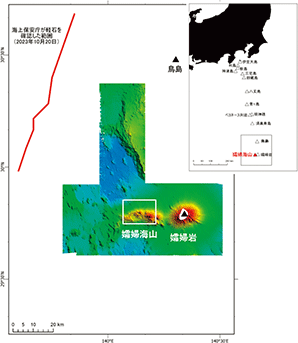 位置図 |