海上交通の安全を守る

海上交通の安全を守る
ふくそう海域における安全対策
東京湾などの船舶交通が特にふくそうする海域においては、船舶の安全かつ効率的な運航を確保するため、東京湾海上交通センターでは海上交通に関する情報を常時把握・分析し、航行船舶に対して、情報提供を行うとともに、巨大船などが航路を安全に航行できるようにパトロールを行う巡視船艇と連携しながら航行管制を実施しています。
また、AIS(船舶自動識別装置)を活用した次世代型航行支援システムを導入することにより、従来のレーダーエリアよりもさらに広い海域において、AISを搭載した船舶の動静把握や情報提供が可能となりました。
-

神奈川県にある城ヶ島灯台
「海の安全情報」による情報提供
気象・海象状況や工事状況、定置網設置状況などの情報の把握不足による海難を防止することを目指して、海で活動する方々に向けて、パソコンや携帯電話のインターネット、テレホンサービスなどで、海の安全に関する情報を提供する沿岸域情報提供システム (海の安全情報) を運用しています。
このシステムは、リアルタイムな情報を「誰もが簡単に、必要な情報を必要なときに、誰にでも分かりやすく」入手できるもので、管内の各海上保安部で運用しています。
また、航行船舶や操業漁船などの安全を図るため、全国各地の灯台などの航路標識において、局地的な風向・風速・風浪などの気象の観測を行い、その現況を無線電話により定時に通報するほか、テレフォンサービスなどで随時提供しています。
沿岸域情報提供システム (海の安全情報)
海上保安庁では、プレジャーボート、漁船などの船舶運航者や磯釣り、マリンスポーツなどのマリンレジャー愛好者の方々などに対して、全国の海上保安部等からリアルタイムに「海の安全に関する情報」を提供する「沿岸域情報提供システム」 (海の安全情報) を運用しています。
「海の安全情報」についての詳細は海上保安庁のページをご覧ください。
地域に密着した海難防止活動
全国各地で多くの船舶が海難に遭遇し、多くの尊い命が失われています。これら海難発生原因の約7割は、見張りの不十分や操船不適切といった人為的要因によるものです。
海難を防止するためには、海難防止思想の普及・高揚並びに海難防止に関する知識・技能の習得が有効であることから、管内各地で海難防止講習会の開催や訪船指導等を行うとともに、毎年春、夏、秋には「海の安全運動」を実施し、巡視船体験航海等の各種イベントを通じて、広く国民に対して海難防止を呼びかけています。
-
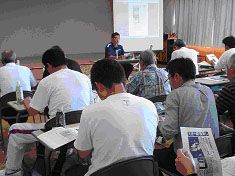
海難防止講習会の様子
航路標識の種類と活用
航路標識は、船舶が自船の位置を確認し、目的地まで安全かつ効率よく航行するために必要不可欠なものです。
航路標識には、灯光・形象・彩色によりその標識の位置または航路や障害物の所在を示す・灯台・灯標・灯浮標などの「光波標識」、電波により航路や障害物の位置情報を提供するAIS信号所などの「電波標識」、電光表示板などにより、海上交通に関する情報を提供する船舶通航信号所などの標識があります。
地方公共団体等による灯台の観光資源としての活用等を積極的に促し、海上安全思想の普及を図るため、これを通じて地域活性化にも一定の貢献を果たしていきます。
また、明治期に建設された灯台のうち、歴史的に価値が高いものとして重要文化財に指定された灯台等は保存活用計画に基づき、適切な維持管理に努めています。

犬吠埼灯台のレンズ

御前埼灯台

清水灯台
なお、令和3年に航路標識法の改正により「航路標識協力団体制度」が創設されました。海上保安庁では、航路標識の維持管理等の活動を自発的に行う民間団体等を「航路標識協力団体」に指定し、その活動を支援します。
※令和6年度 航路標識協力団体募集期間:令和6年11月1日(金)~令和6年12月16日(月)
航路標識協力団体制度の詳細は下記ボタンをクリックしてください。
航路標識の老朽化、防災対策と新技術の導入
海上交通の安全を守る重要なインフラである灯台等の老朽化が進行していることからライフサイクルを意識した点検診断及び修繕を的確に行い、灯台等の長寿命化を図ります。
激甚化、頻発化する自然災害に対し、灯台の倒壊事故を未然防止するため、基礎部等に海水等が侵入し倒壊の蓋然性が高い灯台等に対し、海水侵入防止対策を実施しています。
また、保守の省力化を図るため、高輝度LEDを活用した新たな光源を大型灯台等へ導入しするほか、灯浮標の流失等の異常を早期に発見するため、灯浮標の位置や蓄電池電圧等も監視する新たな監視装置を導入しています。
-

高輝度LEDを採用した灯器



