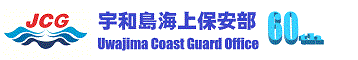新人B 「灯台や灯浮標に使われているLED灯器のⅢ型とかⅤ型とか、何が違うんですか?」
係長A 「何って、光度(光の強さ)が違うんだけど...」
新人B 「マーク1、マーク2とかみたいに、開発・改良した順番かと思っていました。」
係長A 「具体的には、Ⅲ型は有効光達距離3海里が必要な標識に使用するもので、Ⅴ型だと有効光達距離5海里だね。」
新人B 「有効光達距離??? 初めて聞く単語です。」
係長A 「有効光達距離は、航路標識の設計上の基準で、位置・灯質・灯色を十分確認できる距離のことだよ。」
新人B 「海図や灯台表に載っている光達距離とは違うのですか?」
係長A 「そうだね。じゃあ、いろいろある光達距離を整理してみようか。」
光達距離には、、次の4つがあります。
① 光学的光達距離
大気中で減衰・散乱しても計算上見える距離 大気の透過率0.85 限界可視照度0.0000002 lx
② 地理学的光達距離
地球が丸いことから、光が直進して地表面で遮られない最大の距離
③ 名目的光達距離
国際的な統一ルールに従った条件で見える距離 大気の透過率0.74 限界可視照度0.0000002 lx
④ 有効光達距離
航路標識の設計時に用いる距離 大気の透過率0.74 限界可視照度0.000001 lx
官報の告示など、標識のスペックを表すのに用いる光達距離は、①②の小さい方です。
海図や灯台表など、国際的に使用されるものでは、②③の小さい方です。
①の大気の透過率0.85は条件が非常に良い晴天暗夜ですので、③の平均的視程10海里(約19km)(大気の透過率0.74)の方が現実的といえます。
②の地理学的光達距離は、同じ光度でも、標識の光源の高さや観察者の目の高さで違ってきます。
海上保安庁では、観察者の目の高さを5メートルで算出しています。(国際的ルール準拠)