|
この灯台の特徴は、西洋に例を見ない世界的にもめずらしい「二重殻複合構造」であり、外壁は石材、内壁はレンガの異なる材料の組合せによる組積造りで、その断面は図のようになっています。
出雲日御碕灯台を含む、明治期に建設された日本の灯台には、灯室の形、その頂部のヴェンチレーター、踊り場の手摺のデザイン、灯塔部に上下一列に並ぶ窓など、スコットランドの灯台との類似点が多く認められます。これは日本の灯台建設を請け負ったイギリスの灯台技師、リチャード・ヘンリー・ブラントンがスコットランド出身であることが関係しています。
ブラントンは、出雲日御碕灯台の特徴である「二重殻複合構造」の元になった、「二重殻構造」を日本で初めて試みた人でもあります。ブラントンは来日するに前に、当時灯台建設の分野で権威だったスティブンソン兄弟から、日本では地震が頻発するから注意するように、との忠告を受けていました。そのためブラントンは灯台建設に際して、耐震性を重要視していたと言われています。ブラントンが耐震のための剛性を持たせることを意図して、この「二重殻構造」を考案したかどうかは、現時点では資料が乏しいので断定することは難しいとされています。しかし、耐震性や得られる材料の強度、施工技術、予算などを考慮したとき、ある程度以上の高さを持つ灯台に適した構造であることは間違いないとみられています。
出雲日御碕灯台は、1900年(明治33年)の起工であることから、外国人技師はすでに存在せず、設計・施工はすべて日本人の手で行われました。設計は航路標識管理事務所の技師で工学博士の石橋絢彦によるものとされています。石を用いて灯台を造るときには、輸送の制約から石材を施工場所近辺より求めるざるを得なかったと言われています。そのため、その石の性質や石工の技術、現場の状況などを勘案して、それにあった構造法を考える必要があったと思われます。出雲日御碕灯台の場合、外壁の石材は、島根県松江市美保関町森山の硬質の岩から切り出し、境港から海路54海里を帆船で日御碕に近い宇龍のおわし浜まで運びました。海岸から約300メートル離れた現場までは、丸太組みの運搬用桟橋を仮設し運搬したとされ、その際に人力に頼らざるを得なかったことが石材一つの大きさを決める要因であったかも知れません。また、さほど強度を期待できない石であったことが「二重殻複合構造」の採用をうながしたのかも知れません。いずれにしても、当時日本一の高さを誇る灯台を、日本の実情に合わせて西洋技術を応用し、日本人だけで計画どおり造り上げることできたことは、ブラントンによる技術導入か四半世紀を経て、洋式灯台を基礎にした灯台築技術が完全に根付いたことを示しています翌年の水ノ子島灯台を最後に、以後鉄筋コンクリート造による灯台建設が一般的になるこを考えると、出雲日御碕灯台は日本における組積造りによる灯台建設技術の最高峰であると評価出来ます。 |
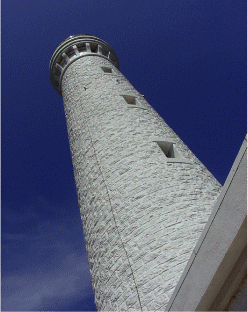
 |
内側から見た「二重殻複合構造の様子
向かって右側がレンガ積壁、左側が石
積壁。ブラントンが建設した犬吠埼灯台・
尻屋埼灯台はレンガのみによる「二重殻
構造」です。 |
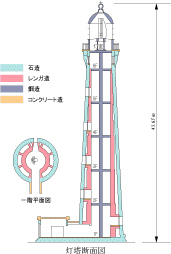
 |
|